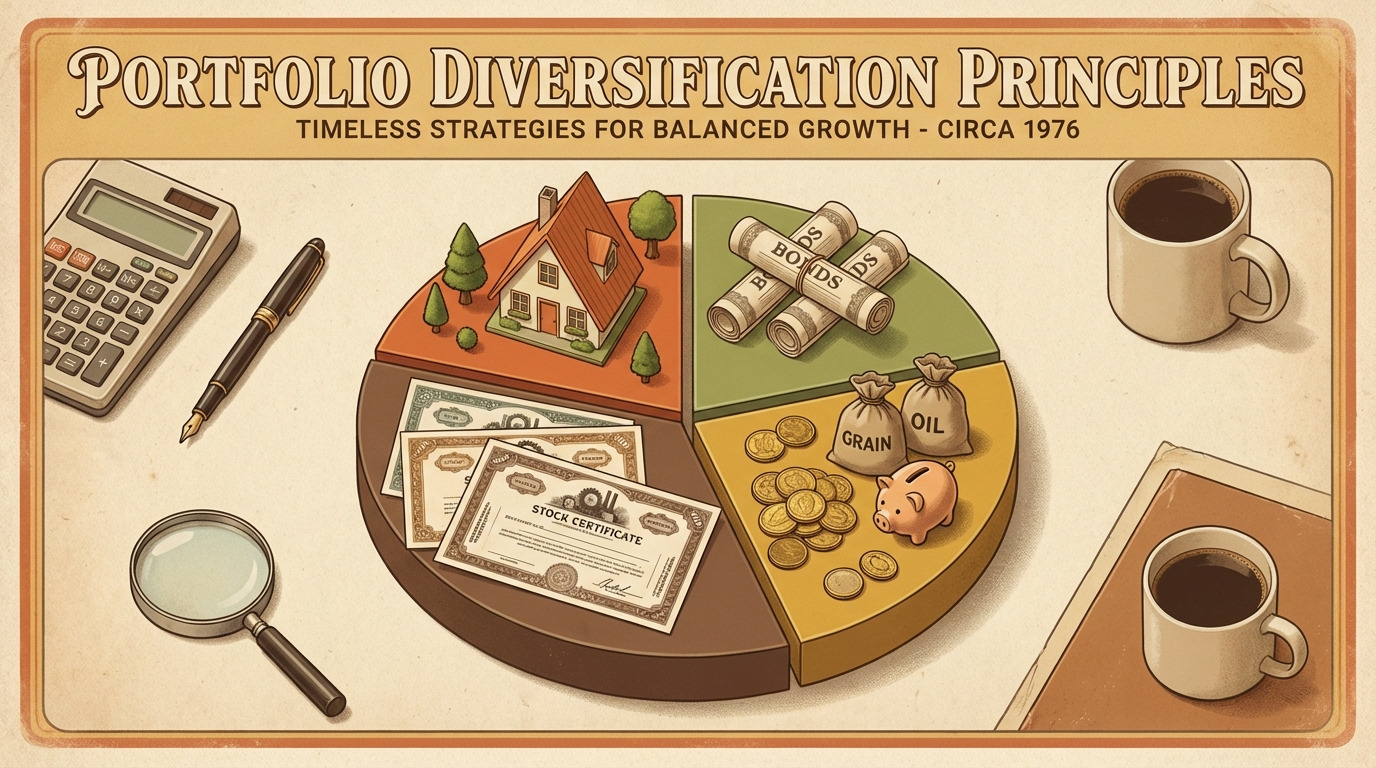生成AI(人工知能)の進歩とバリエーションの発展はすさまじく、身の回りでも「あのAIがよい、このAIがよい」との意見が飛び交っている。職場では生成AIを活用しての業務効率の改善、生産性向上が日常的に言われている。最近はリスキリングと言えば、「AIを使いこなす」と同義になりやすい。
しかし本当にそうなのか。我々がいま磨くべきは、もっと人間的なスキルではないのか――。こう説くのが本書『AI時代に仕事と呼べるもの』だ。AIが代替できない、すなわち「人間に残された」価値ある仕事の定義を説くとともに、失敗を重ねてきた著者自身の経験を交えて具体的な行動指針を差し出している。
本書で「価値ある仕事」とは「顧客に提供する価値が高い仕事」を指す。顧客にとっての価値や顧客視点は、あらゆる業種で重視されていることだ。生成AIを使えば個人的なパフォーマンスが高くなったような気がしてしまうが、改めて「顧客や関係者の目線に立つ」という仕事の基本に立ち返らせてくれる。その意味では、既存スキルや経験の強化、学び直しに役立つ書と言えそうだ。
著者の三浦慶介氏は、企業の成長支援を手掛けるグロースドライバー(東京・渋谷)社長。サイバーエージェント、リヴァンプ、グロース上場企業スパイダープラスのCMO(最高マーケティング責任者)を経て2025年に独立。現在は「AI時代の人材育成×事業戦略」を専門に、事業成長の伴走支援と知見の体系化に取り組む。
AI時代に高まる「レビュー」の重要性
人間ならではの価値を生むために必要な仕事とは何か。著者によれば「経験知を積む」「決断する」「レビューする」、そして「フィジカルで価値を生む」の4つだ。経験知(経験値ではない)、決断、レビューは、最後のフィジカルの要素に支えられているため、著者はこれらをまとめて「3+1の価値」と表現する。
それぞれを簡単に説明すると、経験知を積むとは、自らの経験・行動に基づいた知見を蓄積すること。決断するとは、「目的」と「得るべき成果」を決め、行動方針を立てること。レビューするとは、仕事の進め方やアウトプットが「目的に沿っているか」を確認すること。そして、人間にしかできない身体的な力を通じて先述の3つを発揮していくのが、フィジカルで価値を生むこととなる。
この中でも、レビューは昨今重要になっているように感じる。AIを使うとアウトプットが量産されるため、自分が何を求めていたかや、品質の良しあしが分からなくなる時がある。著者は、AI自体にレビューさせるやり方もあるが、もし成果物を公開して事故や損害があっても、AIは責任を取れないと指摘する。生成AIを使う以上、かならず人間が確固たる軸でレビューする必要があるのだ。
レビューする際は、「顧客のためになっているか」が基準となると著者は説く。例として挙がるのが、Cygames(サイゲームス)によるゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の開発経緯だ。2018年冬にリリース予定だったこのゲームは、同年12月半ばに延期が公表された。2年以上たった2021年にようやく正式にリリースされ、大ヒットゲームとなった。
延期が発表された時点で、数十億円規模の開発・プロモーションコストがかかっていたはずだ。それでもリリースを取りやめたのは、「顧客の期待水準に満たない」という社内レビューが働いたためだと著者は見ている。顧客視点で精度高くレビューし、場合によってはそれまでの成果を捨て、軌道修正する。こうした審美眼や決断力こそ、人間が発揮するべき価値ある仕事の一角なのだ。
フィジカルな健康を大切に
人間の身体性が持つ価値についても一章を割いて説明している。例えば、対面で会うことの重要性。オンラインではなく対面で会い、何度か場を共にすることで、相手のことが分かる以上に自分のことを伝えられるという。何度も足を運んだ営業先に自分の人間性が信頼され、大きなコンペがあるときに声をかけてもらえたなど、チャンスが広がるケースもある。近頃は飲みニケーションが再評価の兆しもあることを考えると、フィジカルに人と関わることの意義はどんな時代でも小さくないと言えそうだ。
そして、著者が最後に強調するのは、肉体が「健康」であることだ。人とリアルで会うにせよ、AIを使うにせよ、それに向き合う人間の脳と肉体は疲弊する。とくにAI時代には、高速・疲れ知らずのAI相手に、レビューや決断を迫られることが増加し、生身の人間は消耗する一方だ。健康が失われては、結局人間ならではの「3+1の価値」は発揮できない。つまり、健康という資本を大事にした上で、戦略的かつ多角的に動ける人が、これからは大きな成果を発揮すると説く。
生成AIをうまく使い、短時間に成果を上げるだけが仕事なのではない。人間の仕事はもっと広く、複合的で、伸び伸びしたものだ。そんな風に考えられる一冊である。